旬のお届け 秋田の山菜
おまかせセット
現在の山菜(4月末頃)
=しどけ・ほんな・こごみ・くれそん・行者にんにく=などです。
(季節の旬を各種3~4人前4~5品種入っています。内容については季節要因がありますのでその都度下記メールにて問い合わせ下さい。) ![]()

ひろっこ(野蒜・ののひろ)

春の使者・フキノトウ
(バッケ:秋田県の花)

春一番に芽を出す山菜
「あざみ」
ノビルの若い芽のこと。秋田県南地方では春先に雪の下から掘り出して食べる
。疲労回復・風邪予防に効果のある硫化アリルは長ネギの約2.5倍。老化・
ガン予防に効果のあるポリフェノールは成長したノビルよりも多く含まれる。
雪の中から取り出すと、緑はなくて黄色と白いひろっこが出てくる。独特の
香りと風味は、雪国の味だ。生まれ故郷の田の畦で、引く抜いた野蒜を味噌を漬けて食べた幼い日
野の香りの野蒜・・・ひろっこも雪融けまで待つと同じ顔になる
採り方・食べ方
採取は、手でひねりながら採る。まだ開かない若葉は、天ぷら、刻んで味噌汁。バッケはアクが強く、敬遠する人も少なくないが、フキ味噌、揚げ田楽にすればアクも少なく美味。独特の苦味が山菜マニアに好まれている。
採り方・食べ方
アザミの旬は、雪消え直後に開いたロゼット状の若葉である。葉の先に刺があるので、軍手は必携。手で採らず、根を引き抜かないようにナイフで切り取る。刻んで味噌汁の具、天ぷら、茹でてゴマ味噌和え、おひたし。
モリアザミの初夏の若茎は、ゆでて水にさらし、皮をむいてからマヨネーズで食べると美味い。

クセもなく万人に好まれる山菜・
コゴミ (クサソテツ)

山菜の女王・アイコ
(ミヤマイラクサ)

山菜の王様・シドケ
(モミジガサ)
採り方・食べ方 谷沿いの斜面や渓流沿いに生える。伸び始めた葉の先が、ゼンマイのようにしっかり巻いている若芽が旬。山菜として食べるシダ植物には、ゼンマイ、ワラビなどがあるが、アクが強く、下ごしらえが面倒だ。ところがコゴミは、アクもなく下ごしらえも簡単で、万人に好まれる山菜である。
葉が開く前、丸く巻いた若芽の先の部分をつみとる。茹でると鮮やかな緑色と特有の香りがする。茹でたものをマヨネーズ、けずり節と醤油、ピーナッツ和えなとが美味い。生のまま、衣をつけて揚げ物、汁の実、煮物、炒め物にも最適。
採り方・食べ方
全草にトゲがあるので、軍手を忘れずに。腐葉土が厚い所では、土中に入った茎の部分は意外に深い。できるだけ深い根元から採取するには、手前に折り返すように慎重に採取するのがコツ。茹でてから冷水にさらし、一本一本皮をむいてから適当な長さに切る。マヨネーズや醤油をつけて食べると美味い。炒め物、汁物、和え物など。
食べ方 上手な茹で方は、まず塩を一つまみ入れて大鍋を沸騰させる。熱湯に山菜を根元から入れ、再度沸騰したらOK。茹ですぎると風味を損なうので注意が必要だ。茹でたら、素早く冷水にさらし、お浸しで食べると美味い。アイコと違って山菜特有のクセがあるので、敬遠する人も少なくない。そんな方は、天ぷらにして一塩ふりかけ食べるとクセがなく美味しく食べられる。他に煮びたし、ごま和えなど。

雪国を代表する山菜の一つ・
ホンナ(ヨブスマソウ)

山菜の横綱・山ウド

清冽な水のシンボル・ヤマワサビ
採り方・食べ方
手で軽く折れる硬さのところから採取する。料理は、おひたし、天ぷら、ごま和え、酢味噌和え、油炒め、汁の実に。アクは少なく、鍋物に入れても、煮物に入れても味が良くしみて美味しく食べられる
食べ方 独特の苦味と風味は山菜の横綱として珍重されている。上部の葉の部分は天ぷら、白い根元は生食が定番。根元部分の皮をむき、酢水にさらしてから、酢味噌などをつけて食べる。皮をむいてから油で炒めるても美味い。味噌汁の具、茹でてごま和え、味噌和えなど。
食べ方 ワサビの太い根の部分は、よく洗い、ナイフで皮を削り取ってから、すりおろし刺身などの薬味に。写真は、全草をよく洗い、ワサビを細かく刻んだもの。これを小さな密閉容器に入れ、万能つゆ(5倍濃縮程度)を薄めず注ぎ一晩漬けこむと美味い。また、容器に刻んだワサビを入れ、熱湯を注いだ後、蓋をし冷蔵庫で冷やすと、辛味もアップする。生のまま細かく刻んだものを味噌汁や麺類の薬味として食べても美味い。他に茹でてから、おひたし、和え物など。

ウルイ(オオバキボウシ)
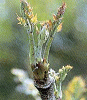
たらの芽

ゼンマイ
採り方、食べ方
葉の開かない丸まっているものが旬、その茎の部分をナイフで切り取る。若い葉でも苦味が強いので、葉の部分は手でちぎり、茎の部分だけ採取する。刻んで味噌汁に入れると、ヌメリがあり美味い。茹でてから、冷水にさらし、マヨネーズ、ワサビ、ゴマなどで和える。また、一夜漬けも独特のヌメリと歯応えがよく美味い。
食べ方 誰もが知っている山菜の一つ。日当たりの良い林道沿いや伐採跡地に多く生える落葉低木。タラノメは棘だらけの枝の先端に芽がつく。枝先の一番芽のみを採取する。二番芽、三番芽を採り続けると木は枯れてしまうので厳禁。ご存知天ぷらが定番。
ぜんまい料理 冬期間の野菜不足や栄養補給源として食材を組み合わせてお正月に作る一品。
ぜんまい・昆布・ゆり根・黒豆を利用して煮物を作り、年の初めに豆・ゆり根・昆布を食べて、「また今年も1年 まめで喜んで暮らせる様に」という願いがこめられている。





フキ
みず 食べ方・その1 ミズタタキ・・・ちょっと面倒だが、最も美味しい調理法がミズタタキ。粘り気のあるアカミズ(左の写真)を使う。葉とヒゲ根をとり、皮をむく。熱湯にさっとくぐらせてから冷水にさらし、水気を切る。まな板の上にのせ、すりこぎで叩いてつぶし、さらに包丁で細かく切る。トロロ状になったら、すり鉢に入れ、味噌とサンショウ(ニンニクも美味い)を混ぜてすり合わせると完成。
食べ方・その2 ミズのコブ・・・9月頃になると、茎と葉の付け根に小さな丸いムカゴ状の実がつく。秋田ではミズのコブコと呼んでいる。カモシカは、ミズのコブだけを選り分けて食べるくらいで、人間にとっても大変美味い。右の写真は、ミズのコブだけを採取したもの。さっと湯がいてから、塩昆布などと混ぜて即席漬けが一番。歯ざわりが良く、粘り気のある甘さがあって、とにかく美味しい。ミズの一般的な料理は、味噌汁の実、おひたし、油炒め、和え物。
食べ方 フキはアクが強く、そのままでは食べられない。熱湯で茹でてから、冷水にさらした後、一本づつ丁寧に皮をむき、調理する。フキの油炒め、煮物、味噌汁の具も美味い。

さしぼ

こしあぶら
「さしぼ」とはイタドリの芽のこと。【保存する】
上記処置後にフリーザーパックに入れて冷凍保存です。家庭用冷蔵の冷凍室 で十分保存できます。フリーザーをお持ちのかたはそれに保存しましょう。おおよそ半年間は鳥海山特有の味わいを保つことができます。
【日持ち】
解凍後または冷凍せずに処置後に冷蔵保存した場合はおおよそですが3日~ 4日くらいは安心して食べられると思います。ただ、どんな食材もそうですが 異臭や変色、変質している場合は迷わず捨てましょう。
【調理方法】
1.おひたし
一番オーソドックスですが一番美味しい食べ方だと思います。ただし茹ですぎ には注意しましょう。冷凍からそのまま茹でても平気です。枝豆を茹でるときのタイミングでしょうか。一煮立ちしたらすぐにざるにあけて冷水に戻さずしばらく水分をとばした後に食べるのが私は好きです。そしてもちろん醤油とマヨネー
ズ♪まあマヨのかわりに鰹節等のほうが一般的ですか?
2.天ぷら
一般的な食材と同様の作り方でいいでしょう。これまた美味ですが、やはりぬめりや酸味も残りますので好き嫌いの分かれるところかと思います。
3.みそ汁
これまた普通にみそ汁の具として入れますが、ぬめりと独特の酸味があるために好みが分かれるところですので要注意。個人的にはあまり好まない食べ方
です。
食べ方
山菜こしあぶらは、たらの芽の兄弟分。
たらの芽の木と違い、山菜コシアブラはトゲがなく大きな木を見つけると量的にもとれるかも・・・
味わいと食感はたらの芽よりこしあぶらの方がやわらかい。
見た目はたらの芽よりこしあぶらの方がとてもきれい。
「てんぷら」がお勧めです。

まがり竹の子

わらび
食べ方 採取したタケノコは、ナイフで縦に切れ目を入れてから丁寧に皮をむく。長刀のように伸びたタケノコは、節々が硬いので硬い部分を切り落とし、軟らかい部分のみ食用として使う。アクがほとんどなく、味は上品で淡白、香りや舌ざわりもすこぶるよく、雪国では最も人気が高い山菜の一つ。皮をむかずに、焚き火で焼いてから、味噌やマヨネーズをつけて食べるのも美味い。もちろん、味噌汁の具、天ぷら、煮物なども美味い。
食べ方 アク抜がポイントです。ここでは重曹を使っていますがわらの灰をつかって
アク抜きをする本格的方法もあります。 ①大きい鍋で水を沸騰させる。 ②そこに食用重曹を入れてからわらびを入れる。
③2~3回かきまぜるだけ(沸騰させない)④火を止めてからフタをし、そのままおいておく
1~2時間(目安)したらフタをはずし冷やす。 (さわってみて柔らかくなっていたらフタをはずしましょう) かためが好きな人は火を止めてからフタをせず、そのまま冷やす。数時間おいたほうがアクも抜けて苦くない。⑤茶色の水はアクなので水は入れ替えます。
⑥つまみ食いをして適度のカタさだったら水をすて冷蔵保存します。
⑦チャック付きの保存袋に入れて保存するのがいいようです。【食べよう♪】
上記下ごしらえのあと、または冷蔵保存してあるものを食べましょう。
3~4cm長に切りそろえます。以下代表的なわらびの食べ方です。
● おひたし風 しょうゆ&マヨネーズ
しょうゆ&かつおぶし
● みそ汁の具 すでに食べられますのでぐつぐつと煮る必要はありません。
煮すぎると柔らかくなりすぎてドロドロになってしまします。
できあがり直前にみそ汁に入れてもじゅうぶんでしょう。
● その他 ☆ わらびを炒めたあと玉子とじ
☆ ごま油としょうゆをお好みでからめる
☆ とりたては焼いて味噌&マヨネーズなどで食べても◎
 |
行者にんにく
食 べ 方
にんにくとニラを足したよう。クセモノでうまい!葉は中華ぽいエキゾチックな香りもする
赤い薄皮(ハカマ)ごと食べてもよいが、内側に土が入っていることが多いので、取って洗った方がいいでしょう
葉の分かれるマタにも土が入っているので流水をあてて洗うとよい。
油炒めが一番
炒め上がりにしょうゆをかける
強烈なニンニク臭にほのかな中華風の香りが抜群。
おひたし(ゆでてしょうゆ)はマイルドで甘みがある
生で白い茎を食べてもよい(つけるならみそ)。
秋田の逸品を全国お手元に
秋田ふるさと館OTA
〒014-0805
秋田県大仙市高梨字水里36-3
代表 太田欣次郎
電話 0187-63-6080(FAX共用)
 ご注文お問い合わせはFAX又はメールを下さい。
ota@obako.or.jp
ご注文お問い合わせはFAX又はメールを下さい。
ota@obako.or.jp